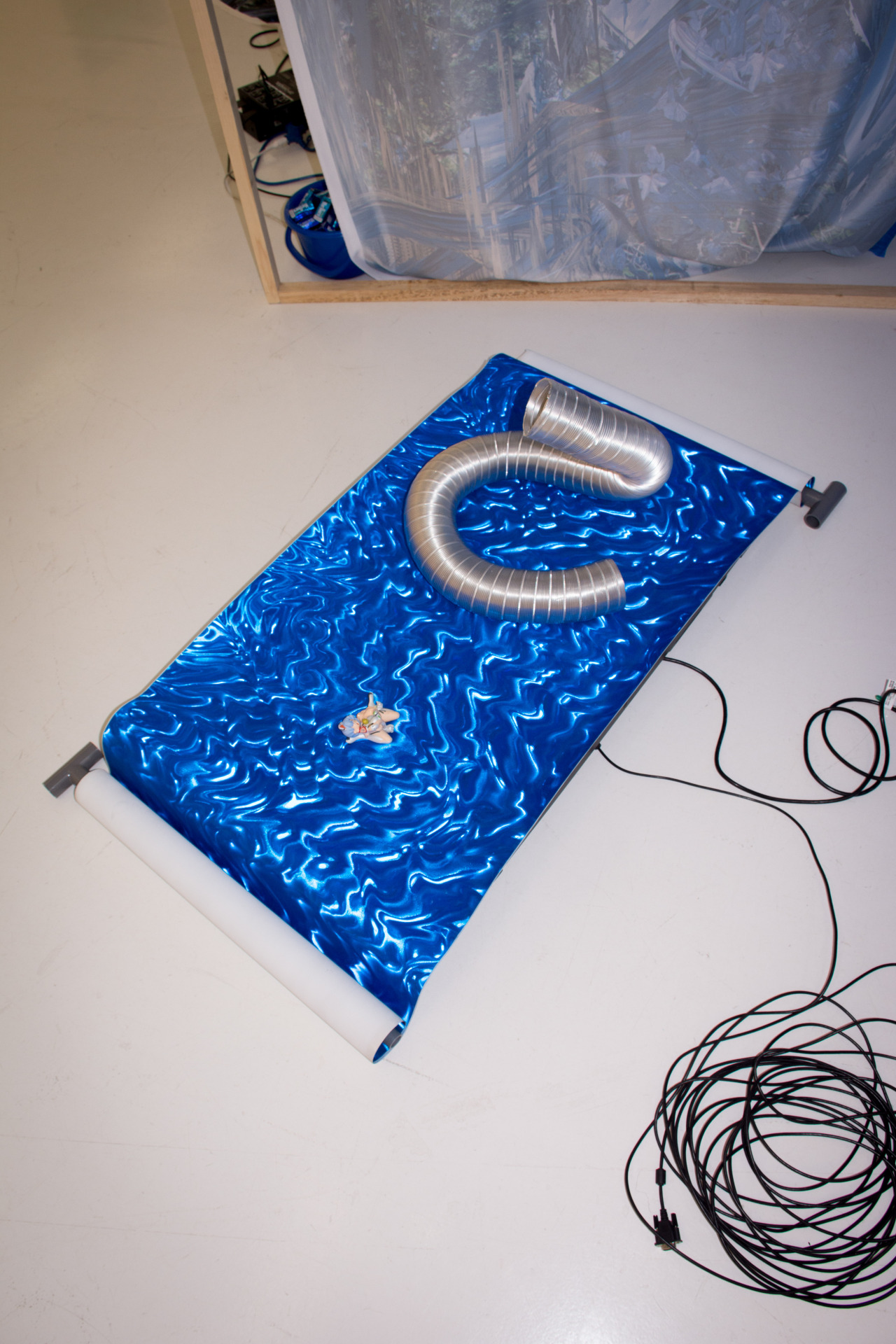vaporな物語の条件
アトリエにあった物品、映像(印刷物はrei nakanishi)

この文章はインターネットに関するものです。今回、ボクはインターネットから新しい文学を提示します。
それはツイッターやtumblrなどにおける様々な投稿――テキスト、画像、GIF、vineなど――によるものです。しかしこれらが「文学」であるというのは少し受け入れがたい提案かもしれません。これらの投稿はあまりに日常的すぎるし、重みが無さすぎます。そこでインターネットにおいて表示される表象が「何を」あらわしているのか、それらに価値付けを行うとするなら「何に」なるのか?という問題を整理するなかで説明を行いたいと思います。結論を先に述べるならボクはこれら の表象(投稿)が表す対象はvaporな(霧や霞のような)風景であり、それらは新しい文学としての 価値を持つのだという提案をしたいと考えています。そしてボクはその新しい文学を「非実存文学」 と名付けます。
この文章ではモチーフとしてtwitter、tumblrを扱います。twitterはアメリカで2006年にサービス が開始したインターネット上のコミニュケーションサービスです。140文字までのテキストの投稿が可能で、投稿された文章はツイートと呼ばれます。サービス開始後、画像や動画の投稿も順を追って可能になっていきました。ツイート群はタイムラインと呼ばれる形で、下から上へと時系列に並べられて表示されます。ボクたちはそのタイムラインを高速でスワイプし、リプライを飛ばしたりリツイ ートしたりいいね(♡)する中でコミニュケーションをとります。tumblrもまたインターネット上のサービスですがtwitterとは異なりブログサービスです。tumblrは2007年にサービスが開始されたサービスです。各々が個別のURLを持ち、そこに様々な記事を投稿します。テキストに限らず画像や動画のみの投稿が行われる点、他のブログからリブログ(twitterのリツイートのようなもの)して自分のブログに再配置できる点、美しいデザインのインターフェースが従来のブログとの差異となります。 他にも語られるべきインターネット上のサービスや動向などはありますが今回は対象を絞ることで円滑に議題を進めていきます。
これらの投稿が崇高な風景であり、新しい文学であるというのはどういうことなのか。その説明の ためにはじめに風景と人間の関係というものについて絵画を例にとりながら考えを深めていきたいと思います。絵画において風景とは、宗教的な物語や歴史的な物語の背景として添えられるものでしかありませんでした。ですが透視図法による幾何学的遠近法の誕生によって人々の絵画空間は劇的に変化しました、透視図法による絵画は視点が固定されるため物語を描くのに向きません。そのため幾何 学的遠近法の誕生以降、必然的に風景そのものを描く風景画が誕生しました。
絵画から文学を見ると、近代文学を特徴づける主観性や自己表現という考えが、世界が「固定的な視点をもつ一人の人間」によって見られたものであるという事態に対応していることがわかる。幾何学的遠近法は、客観のみならず主観をも作り出す装置なのである。しかるに、山水画家が描く対象は一つの主題によって統一的に把握されたものではない。そこには一つの(超越論的)自己がない。文学におきかえていえば、そのことは、透視図法のような話法が成立しないならば、近代的な「自己表現」という見方が成立しないということを意味する。
(柄谷行人「日本近代文学の起源」1988)
山水画もまた風景画として捉えらえられがちですが、大自然を意味する山水は道教思想、陰陽五行説などを背景とした主題であって、いわゆる風景画とは異なります。実は純粋な風景画――風景を描くための風景画――というものの歴史は絵画史全体として見てもとても短いのです。それはつまり風景というものの「顔」を見るのは、ただ風景を見るだけでは叶わないということを意味します。風景に宗教的な神秘性や物語性を見出さずに風景画を描くというのはとても困難なことなのです。では風景と向きあうにはどうすればいいのか、そこではある種の倒錯が求められます。ひとつの側面として、風景とは我々にはコントロールすることができない畏怖すべき対象です。その畏怖の想いは絵画 としてパッケージされたとき快楽として働きます。風景画の地位を上昇させたターナーは畏怖すべき自然を大画面に描きました、そして彼は崇高という言葉を用いて風景と人間の関係性のなかで倒錯を遂行し、我々に極上の快楽を提供しました。そのような変換の側面は芸術において必要不可欠です。そして幾何学的遠近法に基づく風景というものは固定された一人の視点によって見られた空間であり、それは「客観のみならず主観をも作り出す装置なのである」という柄谷行人の言葉どおり近代文 学における特徴とも共有されます。
この変換による快楽の生成と近代文学的な特徴をtwitterとtumblrは満たしています。まず絵画からの流れで画像の面から新しい文学を語りましょう。現代において人々はiPhoneをはじめとしたス マートフォンを片手に世界中を歩いています。彼らは絶えず日常を付属のカメラで切り取りインターネットにアップロードしています。そして撮影された写真はアップロードされた瞬間に文脈を保持することができなくなります。いいえ、近年はむしろアップロードする瞬間にすでに文脈は剥奪されています。旧来であればインターネットに画像をアップロードする際はその写真の情報(撮影地や撮影されたイベントなどの状況の情報)が併記されました。ですが近年のインターネットではそのような情報を添付しない美学が横行しています。キャプションが付かない写真。その場合、ただでさえ匿名 性の高いインターネットでは写真の物語性はかなり軽薄になります。また仮にキャプションが付いて いたとしてもアップロードされた画像は本人の意思に反してコピーされたりリブログされて、他のユーザーによって再投稿される可能性を逃れることができません。つまり写真がもつ物語の欠片として の魅力は剥奪され、ただの風景となってインターネットを漂うしかありません(そこに人が写ってい たとしても)。これがインターネットにおける風景の現状です。
では変換による快楽が生成されるための変換対象はなんであるのか?それは現在、全く言語化されていません。そこで変換対象を明らかにしていきたいと思います。では再投稿されがちな風景画像というものが何かというと、かなり強い物語性や文脈性を持っていそうなのに全く読み解くことができ ない画像です。語弊を恐れずにいうのなら意味がわからない画像です。それは状況的な意味不明さの 場合と匿名性の高い超崇高で幻想的な風景という場合などがありますが、どちらにせよ画像からなんらかのを文脈を読み取ることは不可能です。つまりターナーでいう畏怖という面は風景画像において は虚無であり、表象対象は無く、テクスチャしかない画像。それが現代の若者の間で求められている風景です。変換しようにも対象が虚無であるために我々の鑑賞は空振りすることしかできません。その変換の不可能性への没入と連続的なスワイプによる次の画像への移動は現代の大衆文化の本質です。これはファストでインスタントな文化に包まれながらノームコアなファッションをしてきたさと り世代が没入する場所として完成されすぎていると言えるのではないでしょうか。そしてこの風景画 像による美学はテキストの面においても適応されています。原初のtwitterは日常を切り取り他者と共有するためのものでした。ですが日常を読み取ることが不可能であるくらいに断片化されたリアルタイムでないツイート、ツイートに添付されながら文脈の読み取りが不可能な画像。この状態はロマン主義文学とも自然主義文学ともアニメ・マンガ的リアリズム(東浩紀)とも異なる新たなリアリズム であると断言することができます。ボクはこの表象対象が欠如した文学を「非実存文学」と呼ぶこととします。
ここまででインターネットにおける風景の切り取りによる近代文学的な面を紹介できたかと思います。twitterやtumblrはひとりの人間がひとつの世界像をぼんやりと想定しながら、風景を画像やテキストで切り取って描く「アカウント名」の物語です。そこに明確な起承転結はありませんが、文学においてそのような担保された読書体験は希求されるでしょうか?筒井康隆や舞城王太郎が行ってきた様々な試みは破壊的であるがために純文学としてより強く記録されました。そのような先人の仕事と同じようにボクたちがtwitterやtumblrを文学であると認識することで世界は加速し、芸術は開花するのです。
最初の投げかけに戻りましょう。「インターネットにおいて表示される表象が『何を』あらわしているのか、それらに価値付けを行うとするなら『何に』なるのか?」という問いです。インターネットにおいて表示される表象は「vaporな風景」であり、表層しかない「非実存の文学」であるというのがボクの主張です。この論考を通して構造への言及や社会科学的な解体ばかり展開されるインター ネットに新しい切り口を提案できたら幸いです。
「非実存文学」を意識的かどうかは別として、インターネットでそのような展開をしているユーザ ーやアーティストを紹介したいと思います。日本のtwitterにおいてはマソリズム©(@masorism)やurauny(@urauny)、mzks(@mzks_1)などはかなり虚無的な画像やテクスチャしかないような文章を投稿しています。そしてパープルーム(@parplume)はさらに高度な仕事を行っています。美術予備校とその生徒たちがtwitterでコミニュケーションをとるという形で日常的にアカウントは展開されます。そして度々開催される展覧会を通すなかでインターネット演劇的な試みのパッケージおこなっています。
tumblrはその構造的に画像や文章のもつ文脈性が剥奪されてテクスチャのみになりやすいので特 筆することもないのですが、アーティストのBACON(http://bacon-index.tumblr.com)は表象対象 が非実存な世界観を自作の画像によって意識的に展開しています。またインターネットの外側でイン ターネットから派生した表現を行っているアーティストとしてはDIS magazineやJoe Hamiltonなど がいます。彼らは風景画像のような没入不可能な場所への没入のようなことをテーマに作品を発表しています。