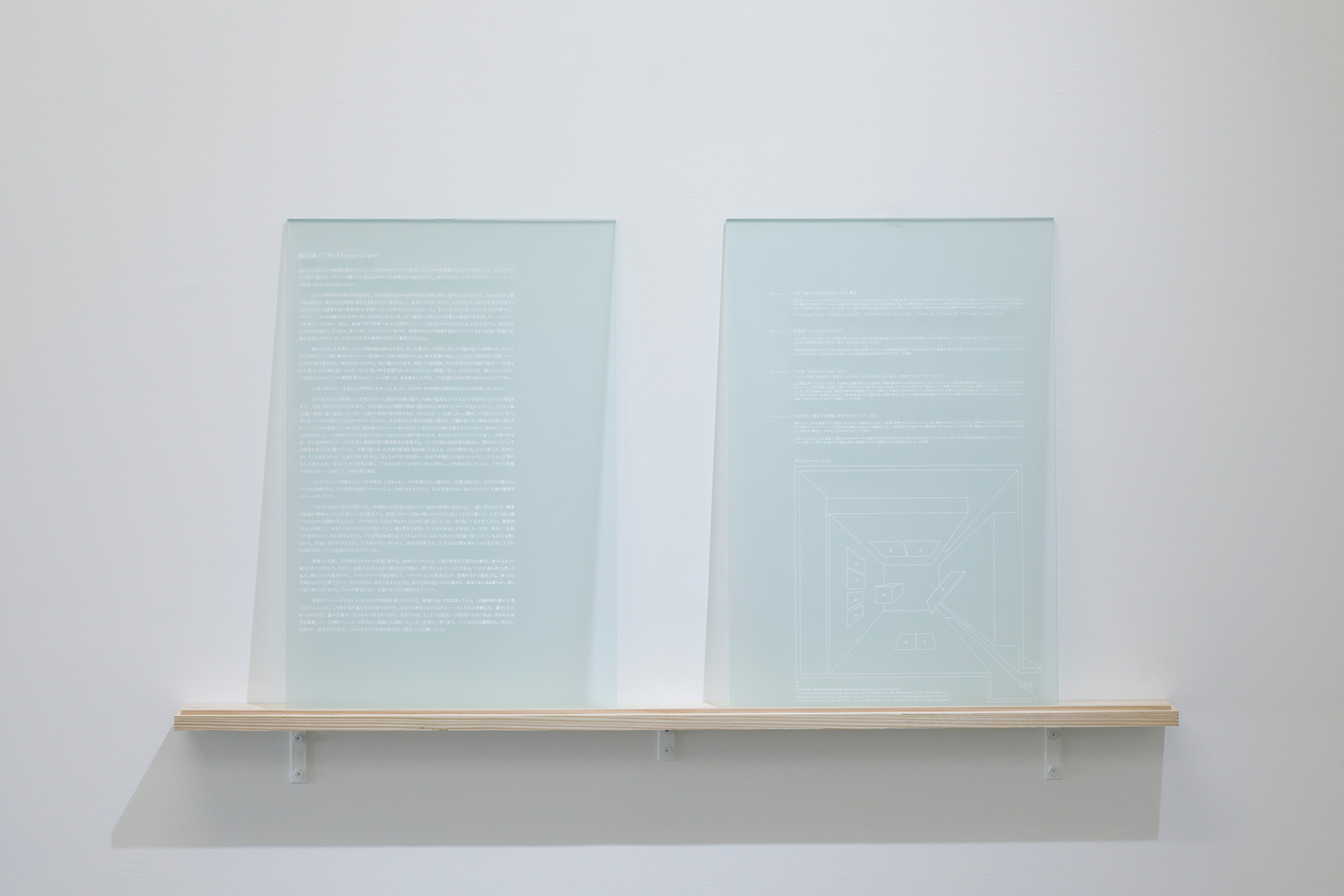余白
SNOW Contemporary

ステートメント
本展の英題として与えられた「Marginalia」とは「テクストの余白に書き込まれた注釈や挿絵、落書き、装飾など」を広く意味する単語で、中世ヨーロッパで写本を行う際にあしらわれたものを起源としています。そしてこの言葉は、書店で購入した本に線を引き、要約や思い付きなどを書き込むことをも意味します。つまりテクストの物理的な余白において、人間は時間を超えて他者と対話し、そのシニフィエ(記号内容)を身勝手に変質させるのです。こうした過去と現在の対話は、時間の恒常的な流れを攪拌し、孤独の時間を創造します。しかしスマートフォンの上で、少しでも速く話し/聞くことを強いられる情報環境において、そうした時間はどこにあるのでしょうか?
こうした問いを出発点として、本展は企画されました。ここでは展覧会において展示される作品と、展覧会に付されるテキストの関係が再考されます。会場には個別のコンテキスト=物語を把持する複数の作品が集められると同時に、布施の手によるフィクション=物語が寄せられます。展示作品とフィクションは、互いを自らの物語の「余白」(marginalia)として参照し合いながら、ひとつの体験を立ち上げるでしょう。
また本展における作品の選択は、不連続な身体を露出することを意図して行なわれました。これらの作品に内包されたいくつかの境界——人間とアンドロイド、オートメーションと偶然性、現在と未来など——は、個別のアーティストの制作行為によって様々に架橋されます。彼/彼女の制作は、人間でありながら機械であり、男でありながら女であるサイボーグを想像する瞬間のように、私たちの身体を脱/再文脈化することで、その不連続性を浮き彫りにするのです。
しかしそれとは関係なく、それぞれの事物に注釈を加え別のコンテキストを構成するフィクション。それは言語が思考を、そして世界の形を確定するという「サビア=ウォーフの仮説」を元にした物語です。そこでは不安について語られます。不安は恐怖とは異なり対象や原因、その主体すらもよく分からないものです。つまりそれは感情というよりひとつの状況であり、現在の不在のなかに身を置くことを意味します。では複数の異なる言語(例えばジョージ・オーウェルの『一九八四年』やテッド・チャンの『あなたの人生の物語』で異星人が使用する言語)において不安はどのようなものとなるのでしょうか?
不安を世界の余白=未来についての思考として捉え直し、展示作品とテクストの関係を実験すること。それが『余白/Marginalia』です。
展覧会概要
会期:2020年2月22日(土)-3月21日(土)
休廊:日・月・火・祝日
会場:SNOW Contemporary
住所:東京都港区西麻布2-13-12 早野ビル404
キュレーション:布施琳太郎
参加作家:小松千倫、髙橋銑、中村葵、村山悟郎
主催:KENJI KUBOTA ART OFFICE
助成:公益財団法人東京都歴史文化財団 アーツカウンシル東京
メディア紹介、批評など
→ 美術手帖 — 余白
→ 美術手帖 — AKI INOMATA「つながりからの隔絶、機械への憧憬」
展覧会内容
空間に置かれた作品についての説明と、小説が、それぞれ磨りガラスの上に印刷されて掲示されていた。以下では展示風景とあわせて、それらのテクストを示す。

小松千倫「Paladin Mode」2017年
2017年にニューヨークのオフサイトキュレーションプロジェクト「Manila Institute」から、楽曲と画像データ、ビデオを含む同名のアルバムがリリースされた。本展では、このアルバムに含まれた8つの楽曲を再生展示した。銃声やビープ音といった具体的な環境を想起させる音と、複数の楽器が重なり合う聴覚体験は、シミュレーションされた空間とBGMが交配されたコンピュータゲームの体験を想起させる。それと同時に左右のスピーカーへと流れるように重心を切り替える続ける音は、ゲーム空間において目まぐるしく視点を回転させながら移動する際の身体性へと私たちを投下するだろう。(文:布施)
1「Dumnp 可」1:44
2「Paladin Mode」14:27
3「76errrrrs」3:49
4「-=三」2:35
5「6ixty」2:18
6「Dent」4:30
7「V3」3:56
8「Header」3:13
村山悟郎「撹乱する機械と再生のドローイング」2020年
撹乱によって、その組織体にできた空白を、再生するような働きがある。もとあった組織を再現するのではない。たとえば、脳に損傷がおきたとき、リハビリによって目指されるのは、新たな神経回路の形成である。機械によってスケールフリーに再生産される撹乱と再生は、その組織体において、組織化の一部を成すように構成されうるであろうか。もしそうであれば、環境によって安定的に再生産される撹乱もまた、組織体の構成の一部となる、と言えるかもしれない。(文:村山)
本作におけるストロークは、画面上に既に引かれたストロークに創発されることで生成されたものである。これまで村山はこうしたプロセスに基づいた平面作品を多数制作してきた。本作ではカッティングプロッターを用いて、同形に切り抜かれた複数の紙片を再構成することで、創発のプロセスを多層化している。(文:布施)


髙橋銑「Cast and Rot」2019年
この作品はニンジンに対し、ブロンズ彫刻に用いられるものと同一の保存処置を施したものである。保存処置を通してニンジンは食卓やスーパーに並ぶ姿とは別の形態を帯び、オブジェとなっていく。これは保存・修復行為と制作行為を同一線上に乗せる試みである。(文:髙橋)
髙橋は作品制作と並行して、近現代彫刻の保存・修復に従事している。こうした経験と知識に基づいて本作は制作された。鑑賞者の眼差しに曝け出されたまま外気から遮断されたニンジンは、私たちの生きる時間のなかで、芸術作品が本来的に志向する超歴史的な時間を提示するだろう。(文:布施)

中村葵「Reloaded Body」2019年
アンドロイド開発、共同研究/石黒浩、小川浩平(アンドロイド制作)、池上高志、土井樹(アンドロイドプログラミング)
42の関節を持つアンドロイド「オルタ」は自律的な運動を続ける。その動きは⑴関節の動きのリズムを作るセントラル・パターン・ジェネレータ⑵脳の神経細胞を模したニューラルネットワーク⑶周囲の環境をセンシングして得た情報への反応、に基づいてリアルタイムに組み立てられる。中村はこのプロセスをビデオカメラで撮影した上で、映像ファイルをフレーム毎に分解した。そして各フレームをプロジェクションし、そこに自らの身体のパーツを一致させる様子を写真撮影した上で、映像として再構成したのが本作だ。こうした手続きのなかで生物としての彼女の身体は、アンドロイドを動作させたプロトコルによって一時的に支配され、書き換えられる。そして緩慢な時間のなかで震える彼女の腕の筋肉は、私たちの個別の身体を動作させるプロトコルを露わにするだろう。また本来はマルチスクリーンの作品だが、本展ではそのなかのひとつのビデオを展示した。(文:布施)

布施琳太郎「Retina Painting」2019年
匿名の若者がインターネットへとアップロードしたセルフィー(自撮り)をモチーフとした絵画作品。描画材としてはスプレーが用いられた。より具体的には油性や水性、ラッカーの塗装用スプレーと同時に、塗膜剥がし用のアクリル性のスプレーや水の入った霧吹きを用いて描画を進めた。これらの多様な化学的な性質を持つ塗料は、画家の意思とは関係なく身勝手に化学変化し、相互に侵食/反発し合う。またディテールを描くために画面に近づくスプレーノズルから噴射された塗料は、重力に負けて垂れていく。そして画面から遠ざかって噴射された塗料は必要以上に広い領域を塗膜で覆ってしまった。こうしたプロセスにおいて顔のイメージは描かれると同時に、自ら崩壊していくのである。できあがった表象以上に、こうした一連の変質こそが、私たちが生きる社会から疎外された個別の身体を現すだろう。(文:布施)

布施琳太郎『鏡の墓/The Mirror Grave』
あれからどれだけの時間が過ぎただろう。いま自分が何について思考しているのかを把握することすらできないまま、私たちは何かに怯え続けた。そしてこの震えから逃れるためにそれを覗き込み続けたのだ。あなたもまた、そうだったのだろう——しかしまずは思い出すことからはじめたい。
ひとつの発明が世界の形を変えた。それは私ではないものが映り込む鏡である。他のなにものでもなく、それがあくまで鏡である理由は、覗き込むと同時に覗き込まれるからに他ならない。あなたではないものが、あなたとして、あなたを見つめ返す。これがどのような機構を持つ装置なのかを問うことは、もう私たちにはできなかった。なんだか分からないものに私たちは夢中だったのだ……あるゆる隔たりが世界のなかから消去されていき、そして最後には私たちの言葉から動詞が姿を消した。つまりすべてが等しく、ただ単に「ある」。動詞不在の世界へ私たちは移行した。ここではなにものも否定されることなく存在する。私はあなたであると同時に、石であり、歩くであり、そしてユニコーンなのだ。言語が私たちの認識を規定したのか、あるいは逆に認識が言語を規定したのか。たしかなことは文法が確率に交代した事実だけである。
隔たりを失った世界は、土だ。生殖活動は終わりを迎え、互いを養分として利用し合うことで種を超えた循環がはじまった。自らを保存し、その種を繁栄させたいという欲望から人間が解放されたとき、資本主義が終わった。もはや人間は何も交換しない。ただあの鏡を覗き込み、覗き込まれるだけだ。埃に覆われた都市、腐敗する動植物、それでも飛び交う無数の電波……放置された星で、私が胸に抱いたもの。それが懐古的な思想であったことはたしかに間違いない。だがそれでも、鏡によって土化した世界のなかにひとつの遺物を混入させたいという思いが、私を動かしたのだ。この欲望だけは未来に向けられたものである。
ここまで来るのに、予定以上の時間がかかってしまった。だがそれでも実現の可能性があることは間違いないだろう。
数十年前まで水族館として使用されていた施設の水槽の底に、内側が鏡面加工された巨大な半球が上向きに固定された。完璧な加工がなされた半球だ。その水槽には三種類の液体で構成された液体ダイヤモンドが注がれていく。これは人体より軽い液体、重い液体、そして同一の重さの液体の混合物である。それらは互いに反発し合い、攪拌しても混ざることがない。水と油、というのが例としてはわかりやすいだろうか。屈折率のみが異なる完璧に透明な、三種の色のない液体で水槽が満たされていく。それは複雑にカットせずとも、最高級のジュエリーに嵌め込まれた宝石のような輝きを備えていることから「液体ダイヤモンド」と名付けられた。この液体によって半球の三倍ほどの深さまで水槽が満たされる。私は白いダイビングスーツを着て、水槽の前で目一杯の深呼吸をした。右の手首に腕時計型の携帯端末を装着する。それぞれ異なる屈折率の液体が、攪拌されながら、その境界を失うことなく蠢いていた。水槽の底にあった半球の断面が液体越しに見える。それは楕円になったかと思えば、星形になり、そして姿を消した。七色の光が目を射る。あらためて深く息を吸い、私は呼吸機を口に咥えた——そして爪先から水槽のなかに飛び込む。散乱した光で視界が輝く。下半身が浮き上がりそうになると同時に、上半身が沈んでいった。そのまま無理やり後ろ向きに一回転して、半球の縁を掴む。
これからひとつの実験を行う。この半球は、いまからもう一つの半球によって蓋をされ、完璧な球となる。全方位が鏡によってできた空間である。その内部は液体ダイヤモンドによって満たされる予定だ。私は半球のなかに転がり込んで、右腕の端末のスクリーンをタップした。
下向きの半球が音もなく降りてくる。半球同士が完全に固定され、視界が暗闇に包まれた。一瞬の間をおいて、端末の画面が照明モードに切り替わって白く発光する。眼球のなかで太陽が輝いたかのような眩しさが私を襲った。だがしばらく待つとぼんやりと周囲が見えてくる。バラバラになった私の身体が、そこら中に散らばっていた。首を捻って右を見てみると、視界がぐるんと回転して、失敗したあやとりのように捻れていく。鏡と透明な液体、そして私の身体しか存在しない空間。屈折し、反射した身体だけが、私に見えるものだ。その空間は無限に広大であるようにも、あるいはまぶたの位置で閉じられているようにも感じられた。背後に目をやろうとすると、下半身がすくい取られて、身体が回転する。巨大な私の顔が現れたかと思えば、上下に引き延ばされ、そして急速に小さくなっていった。
無重力とも違う、不定形な力のなかで浮遊し続ける。液体ダイヤモンドは、人間の身体を浮遊させる重さと、沈み込ませる軽さの双方を孕んでいるのだ。全身が四方から引っ張られると同時に、押しのけられているようである。しばらくゆらゆらと漂った私は、腕に付けた端末を外し、ダイビングスーツを脱ぎ捨てた。バラバラになった肌色と白が、空間のなかで散乱する。真っ白な空間のなかに全裸で立っているかのようだ。肩から生えた生毛と、私の左目が捻れながら繋がる。身体のあらゆる部分が、様々に拡大縮小されながら、ひとつの景色となる。五感のすべてが解体されていった。
端末のバッテリーが切れてからどれだけの時間が経ったのだろう。暗闇のなかで私は待っている。この鏡の球を誰かが見つけてくれることを。この球が私の墓になることができるのか、あるいは単なる土になるのか……それを私は実験した。遺された人がいるのならば、墓が必要だ。私たちの一部でありながら、私たちが失ってしまった過去。その回復のために私は、失われた世界を構築した。この鏡のシェルターは世界から隔離され自閉した、しかし世界の一部である。ここにあるのは攪拌され、刻まれ、反復され、保存された形だ。それがあなたの未来の余白として役立つことを願っている。